

古物商許可証に更新期間は何年?
許可証の番号があると信用できる?
古物商許可証について、上記のような疑問を持っているのではないでしょうか?
先に結論から言っておくと、古物商許可証とは公安委員会から古物営業の許可を受けていることを証明する証書で、更新期間はなく無期限となっています。
又、ネットオークションやフリマアプリ、ネット通販では古物商の許可番号を表記している出品者も多いですが、古物商の許可番号が表記されているだけで絶対に信用できるとまでは言えません。
とはいえ、古物商の許可を取得していない一般の出品者よりは信頼出来る可能性は高いと思います。
以下では、古物許可証とはどのようなものなのかや、古物許可証の更新期間、許可番号が表記されている出品者は信用できるのかなどに関する様々な点について分かりやすく解説していきます。
\全額返金保証付き/
\料金・サービス内容を確認/
注意ポイント
当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。
古物商許可証とは?
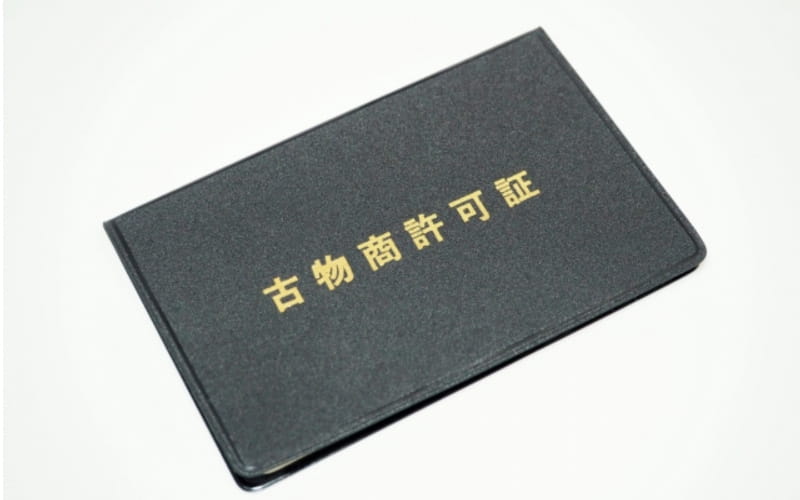
古物商に関する言葉の中で、「古物商許可」と「古物許可証」を混同している人が多いのですが、厳密に言うと別物です。
「古物商許可」とは、古物商として古物営業を行おうとする申請者に対して、公安委員会(警察署)が与える“許可する行為”の事です。
古物商に関して詳しく知りたい方は『古物商とは?を日本一わかりやすく解説|知っておいた方がいい基礎知識 』の記事をご確認ください。
一方で、「古物商許可証」とは、公安委員会(警察署)が古物営業の許可を与えた場合に、許可を受けた証明する証書ことです。
つまり、古物商許可は“許可する行為”、古物許可証は“証書”のことを指します。
古物商の申請が許可された場合に
古物商許可証が交付される
公安委員会(警察署)は古物商許可の申請を受けて、許可をした場合には古物商許可証を交付しなければなりません。
申請書を提出して無事に審査が終われば、提出先の警察署から古物許可証が交付される旨の連絡が電話があるので、警察署に古物許可証を受け取りに行きます。
その際には以下のようなものが必要となります。
- 印鑑
- 身分証明書
- 法人代表者印(法人で申請した場合)
- 委任状(申請者以外が受け取る場合)
個人で申請した場合には、申請人の印鑑と身分証明書を持参することで本人確認ができ、古物許可証を受け取れます。
一方で、法人の場合には代表者の印鑑も必要になるので注意してください。
古物商許可証の許可番号ってなに?
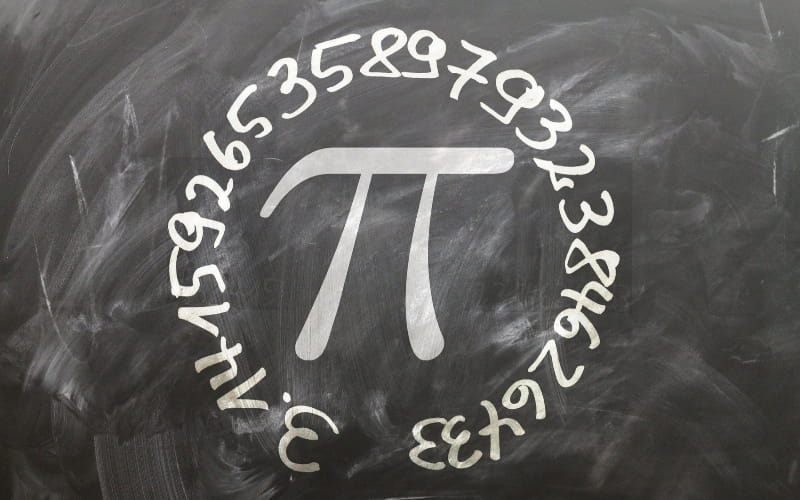
警察から古物営業の許可を取得すると、申請者に対して12桁の許可番号が与えられます。
これが古物商の許可番号と呼ばれる番号で、古物商許可証に記載されます。
そして、この古物商許可証に記載されている許可番号は、古物商プレートやホームページ、販売サイト上に掲載しなければなりません。
古物商許可証の番号を
古物商プレートに表記する
古物商の許可を受けて、古物営業を営む場合には古物商プレートを公衆の見やすい場所に掲示する義務が課されています。
そして、この古物商プレートには古物商許可証に記載されている許可番号を表記しなければなりません。
ですので、古物許可証を受け取ったら、そこに記載されている「許可番号」「古物商許可を取得した公安委員会の名称」「取り扱っている品目」等をもとに古物商プレートを作成してください。
古物商許可証の番号を
インターネットに表示する
営業所において古物営業を行う場合には、古物商プレートに古物許可番号を表記して掲示しなければなりませんが、インターネットを利用して古物営業を行う場合には古物商プレートを掲示することは出来ません。
そこで、インターネットを利用して古物営業を行う場合には、取り扱う古物を掲載している個々のページごとに古物商許可番号を含めた以下の情報を掲載しなければなりません。
- 氏名又は名称
- 許可を受けた公安委員会の名称
- 許可証番号
又、これらの情報は取り扱う古物の個々のページに表記するのが原則ですが、例外としてトップページに表記する場合や、トップページに当該ページのリンクを設定することも認められています。
古物商の許可番号が
表示されていると信用できる?

よくネットオークションやフリマアプリなどで古物商許可番号を表記している出品者を見かけますよね?
これは古物許可証に記載されている許可番号を表示しているわけです。
では、こういった許可番号が掲載されている出品者は信用できるのでしょうか?
結論としては、何の許可番号も表示していない出品者よりは信用できますが、許可番号を表示しているからからと言って必ず安全とも言い切れません。
というもの、古物商の許可というは犯罪歴などの欠格事由に該当しない場合には、適正に申請するば比較的簡単に誰でも許可を取得できるからです。
ただし、申請する際には、氏名や住所などの個人情報を警察署に届け出ることになるので、どこの誰かもわからない一般の出品者と比較すると信用できる出品者である可能性は高いです。
特に、ネット上での取引の場合は、不良品を販売されてそのまま連絡が取れずに逃げられる可能性がありますが、許可番号を表示している場合には警察署に許可番号を照会することも可能なので、音信不通になって逃げられる可能性も低いというわけです。
\全額返金保証付き/
\料金・サービス内容を確認/
注意ポイント
当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。
古物商許可証の料金はいくら?

古物商許可証は料金は0円です。
ですので、古物商許可を取得することが出来れば、お金を払わずに無料で受け取ることが出来ます。
ただ、古物商許可証自体の料金は0円ですが、古物商許可を取得するには20,000円前後の料金が必要となります。
具体的には、古物商許可証を受け取るまでに、以下のような費用が掛かります。
- 申請手数料・・・19,000円
- 住民票・身分証明書交付手数料・・・600円
- その他《コピー代・交通費等》・・・2,000円
古物商許可証はどんな時に必要?
掲示義務はある?

上記でも少し触れましたが、古物商許可を受けて古物営業を営む場合には、古物商プレートを掲示する義務があります。
では、古物許可証そのものを掲示する義務はあるのでしょうか?
結論から言うと、古物許可証そのものを掲示する義務はありません。
但し、古物許可証を携帯し、求められた際には提示する義務が課される場合があります。
それは、「行商」「競り売り」をする場合です。
「行商」とは、営業所を離れて取引を行う業務形態の事で、露天などの仮設の店舗や、古物市場での売買、自動車の訪問販売などが該当します。
一方、「競り売り」とは複数の買い手に価格を競争させて売買を行う業務形態の事で、オークションなどが該当します。
そして、古物商は「行商」「競り売り」をする際には、古物許可証を携帯しなければならず、取引の相手方から提示を求められたら、古物許可証を提示しなければなりません。
万一、「行商」「競り売り」を行う際に古物商許可証を携帯していなかったり、取引相手から提示を求められたにも関わらず提示しなかった場合には、10万円以下の罰金に処される可能性もあります。
古物商許可証の更新期間は何年?

古物商の許可は、行政上は自動車の運転免許証と同じ「許可」という行政行為に該当します。
自動車の運転免許には期限が合って、期限が近付くと免許の更新をしなければなりません。
では、古物商許可にも古物商許可証の更新が必要なのかと言うと、古物商の許可には更新期間はありません。
つまり、古物商許可証が発行された場合には、取り消しなどが行われない限り古物商許可は一生有効なのです。
古物商許可証を取得後
6カ月間開業しないと取り消される
古物商許可証には更新期間はないので、取得するとずっと使い続けることが出来ます。
そういう事もあって、中には「いつか使うかもしれないから、取りあえず今のうちに許可だけ取っておこう!」と考える人もいます。
しかし、古物営業の開業予定がないのであれば、古物商の許可取得はおすすめしません。
なぜなら、古物商の許可を取得してから6カ月以上営業を開始しない場合には許可が取り消されてしまうからです。
ですので、古物商の許可は古物営業を開始する6カ月以内に取得するようにしましょう。
古物商許可証のまとめ
この記事のまとめ
- 古物商許可は「行政行為」、古物商許可証は「証書」
- 古物商許可番号の表示があると少しは信用できる
- 許可番号が表示されているだけで必ず安全というわけではない
- 古物商許可証の料金は0円だけど、許可申請に20,000円前後かかる
- 古物商許可証に更新期間はない
\全額返金保証付き/
\料金・サービス内容を確認/
注意ポイント
当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。
